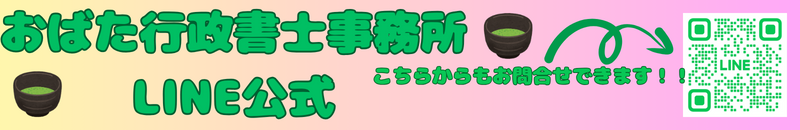ちょっと役立つコラム
11.72023
ユニバーサルコミュニケーションとは何か【静岡県の行政書士が解説】

ユニバーサルコミュニケーションという言葉を耳にしたことはありますか?
近年、「誰にとってもやさしい社会づくり」が叫ばれる中で、この言葉の持つ意味と必要性は、私たちの暮らしにも深く関わるようになってきました。
この記事では、ユニバーサルコミュニケーションとは何か、なぜ今それが求められているのか、そして行政書士としてどのような形でその実現を支援できるのかについてお話しします。
ユニバーサルコミュニケーションとは
ユニバーサルコミュニケーションとは、高齢者や障害者、病気の方など、あらゆる立場の人に配慮したコミュニケーションを意味します。
言い換えれば、「誰にとっても心地よい、思いやりに満ちた対話の姿勢」といえるかもしれません。
もちろん、それは障害や年齢に関係のある方だけのものではありません。たとえば、外国語がうまく話せないとき、体調が優れないとき、環境に不慣れなときなど、誰もが一時的に「コミュニケーションの困難さ」を感じることがあります。
ユニバーサルコミュニケーションは、「すべての人」に関わる、とても身近で大切な考え方なのです。
高齢化が進む日本社会の現状
令和4年10月時点で、日本の総人口は1億2,495万人。
そのうち65歳以上の人口は3,624万人で、実に全体の29.0%が高齢者という高齢化社会を迎えています。
さらに、75歳以上の人口は1,936万人と、65~74歳人口(1,687万人)をすでに上回っています。
また、15~64歳のいわゆる生産年齢人口は年々減少し、少子高齢化の傾向は今後も続いていくと見られています。
高齢者が社会の中心になりつつある今、私たちが日々接する場面でも「わかりやすく伝える力」「相手の状態に応じた接し方」がますます求められていくでしょう。
▶ 詳しくは:令和5年版高齢社会白書(全体版)(PDF版) – 内閣府 (cao.go.jp)
日本の障害者数の実態
日本には現在、以下のような推計があります:
-
身体障害者:約436万人
-
知的障害者:約109万人
-
精神障害者:約615万人
単純な合計はできないものの、国民の約9.2%が何らかの障害を抱えて生活しています。
これは決して「一部の限られた人」ではなく、私たちの周囲にも多く存在している、非常に身近な事実なのです。
▶ 詳しくは:令和5年版 障害者白書 全文(PDF版) – 内閣府 (cao.go.jp)
ユニバーサルコミュニケーションはビジネスにも必要な時代へ
高齢者や障害者のお客様が増えているいま、
ユニバーサルコミュニケーションは接客・サービスにおける必須スキルとも言えます。
たとえば、以下のようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?
-
「事業所で高齢の利用者様とのやりとりに不安がある」
-
「スタッフの接客が一部の方に伝わりにくいと感じる」
-
「障害者支援の制度や運営規程がわかりにくい」
こうした場面でも、「伝え方の工夫」や「環境整備」をすることで、サービスの質が大きく向上し、トラブル防止にもつながります。
ユニバーサルコミュニケーションの第一歩は「心のバリアフリー」
では、私たちに今できることは何でしょうか?
それは、「高齢者や障害者だから特別扱いをしよう」と考えるのではなく、相手の立場に立って行動することです。
相手の状態や気持ちを想像し、ゆっくり話す、視線を合わせる、筆談を取り入れる──
小さなことの積み重ねが、ユニバーサルコミュニケーションの第一歩になります。
そして何より大切なのは、「違い」を障壁にしないこと。
「心のバリア(見えない壁)」を取り除くことが、よりよい社会への近道です。
行政書士としてお手伝いできること
ユニバーサルコミュニケーションの実現には、制度や仕組みの理解も大切です。
たとえば、
-
障害福祉サービス事業の立ち上げ・指定申請
-
利用者様との契約書・説明資料のわかりやすい作成
-
高齢者向けの手続き支援や配慮のある対応方法 など
行政書士として、制度の整備と運営のサポートを通じて、ユニバーサルコミュニケーションが自然と根づく社会の実現をお手伝いできます。
お気軽にご相談ください
「こんなこと聞いてもいいのかな?」
「うちの事業所にも当てはまるかも」
そう感じた方は、ぜひ一度ご相談ください。
わかりやすく、丁寧にお話をうかがい、必要な手続きや制度利用についてご案内いたします。
まずはお気軽にご連絡ください。
誰にとってもやさしい社会づくり、一緒に始めてみませんか?