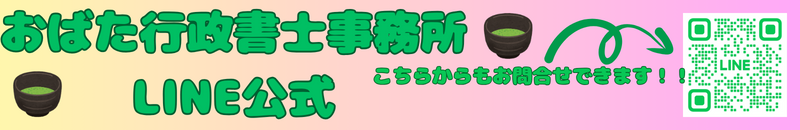- Home
- 障害福祉支援サービス
- 就労支援B型のサービスとはー制度概要と開設時のポイントー【静岡県の行政書士が解説】
ちょっと役立つコラム
9.92023
就労支援B型のサービスとはー制度概要と開設時のポイントー【静岡県の行政書士が解説】

就労継続支援B型は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一種であり、一般就労が困難な方に対し、就労機会や生産活動の場を提供するサービスです。
近年では、地域密着型の支援ニーズの高まりや就労困難者支援の多様化により、B型事業所の開設を検討される事業者様も増えています。
本記事では、制度の基本的な内容から、実際に事業を始めるために押さえておくべきポイントまで、実務的な視点で解説します。
就労継続支援B型のサービス内容とは
就労継続支援B型は、雇用契約を結ばない「非雇用型」の就労支援です。以下の3つのサービス内容が中心となります。
① 生産活動などの機会の提供
パン・菓子の製造、軽作業、手芸品の制作など、利用者の障害特性や地域資源に応じた作業が行われます。利用者には作業に応じて「工賃」が支払われ、金額は事業所ごとの生産体制や経営努力によって異なります。作業は雇用契約によるものではないため、比較的柔軟に参加しやすい点が特徴です。
② 就労スキル向上の支援
就労マナーや時間管理、報告・連絡・相談の習慣づけ、簡単なパソコン操作など、就労に必要な基本的スキルを支援員の指導のもとで身につける訓練が行われます。利用者の中には、将来的に就労継続支援A型や一般就労への移行を目指す方も多く、B型はその第一ステップとして重要な役割を果たしています。
③ 日常生活支援・関係機関との連携
通所継続のための体調管理や生活支援のほか、医療機関や相談支援専門員との連携、計画相談支援との連動も求められます。単なる作業の場にとどまらず、利用者の生活全体を支えるサポートがB型事業所には期待されています。
対象者と「就労アセスメント」の必要性
就労継続支援B型は、以下いずれかに該当する方が対象です。
-
就労経験があり、一般就労の継続が困難な方
-
50歳以上の方
-
障害基礎年金1級受給者
-
上記以外であっても、就労アセスメントによりB型利用が適当と判断された方
特に重要なのが、就労経験がなく、50歳未満かつ障害年金1級の受給者でない方については、原則として「就労アセスメント」の実施が必要になるという点です。
▶ 就労アセスメントとは?
就労移行支援事業所などにおいて、作業観察や面談等を通じて職業的評価を行い、「その方がB型事業所の利用に適しているかどうか」を判定するプロセスです。自治体によっては所定の様式で記録し、計画相談支援員の意見とともに市町村へ提出します。
事業所を運営する側としては、対象者の把握だけでなく、アセスメント機関や相談支援事業所との連携体制の構築が、運営上の重要な鍵となります。
開設を検討される事業者様へ:必要な準備と留意点
就労継続支援B型の開設には、以下のような多くの準備が必要です。
① 人員基準の確保
-
サービス管理責任者(一定の実務経験+研修受講)
-
職業指導員・生活支援員(常勤換算で2.5人以上が目安)
-
管理者
※資格や経歴、雇用契約の内容など、申請段階で詳細な確認が行われます。
② 設備基準の整備
-
作業スペース、相談室、休憩スペースなど
-
面積や区画、衛生面の基準を満たす必要があります
-
開設予定地の用途地域(都市計画法)にも注意が必要です
③ 指定申請書類の作成と提出
-
開設予定地の自治体に対して、障害福祉サービス事業の指定申請を行います
-
提出書類は30種類以上に及ぶこともあり、記載ミスや不備があると受理されないこともあります
-
自治体によっては事前相談・協議が義務づけられている場合もあります
ご相談はお早めに
B型事業所の指定申請は、書類作成に加えて施設の整備や人員の確保、事前協議など、多くの工程を伴います。計画を進めるにあたり、以下のような不安や疑問はございませんか?
-
施設要件や人員基準を満たしているか確認したい
-
計画の段階から行政とどう調整すればよいかわからない
-
必要な申請書類を効率的に準備したい
行政書士は、こうした障害福祉サービスの指定申請や設立支援の専門家として、事業者様の立ち上げを全面的にサポートいたします。
お問合せはこちらから
これからB型事業所を始めたい方、または準備中でお困りの方へ。
指定申請の書類作成、行政との事前協議、要件の整理など、ひとつひとつ丁寧に対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。
おばた行政書士事務所へお気軽にお問合せください。
※参考資料:厚生労働省 障害者総合支援法関連資料、WAM NET、各自治体公開資料