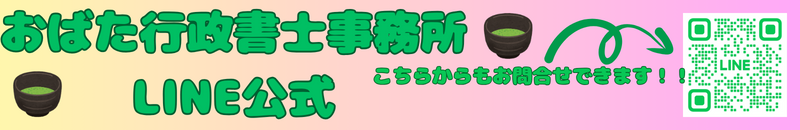- Home
- 障害福祉支援サービス
- 障害福祉サービス、就労継続支援A型の定款はこう書く!【静岡県の行政書士が解説】
ちょっと役立つコラム
7.272025
障害福祉サービス、就労継続支援A型の定款はこう書く!【静岡県の行政書士が解説】
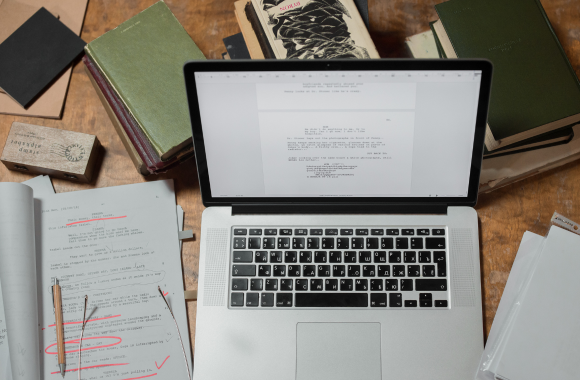
定款の「目的」記載でつまずかないための徹底ガイド
就労継続支援A型施設の開設を目指して法人設立の準備を始めたものの、最初のステップである「定款の作成」で早くも手が止まってしまう──。そんな声をよく耳にします。中でも、「目的」の記載に関する悩みは非常に多く、事業のスタートラインで大きな壁になりがちです。
この記事では、定款作成の際に押さえておくべき「目的」記載の考え方と注意点を、実務的な視点から解説します。
就労支援事業の開設をスムーズに進めたい方は、ぜひ参考にしてください。
なぜ定款の「目的」がそこまで重要なのか?
定款とは、法人の基本的なルールを定めた文書であり、「法人の憲法」ともいえるものです。その中でも「目的」は、法人が何を目的として活動するのかを明示する非常に重要な項目です。
特に就労継続支援A型事業を行う法人にとっては、以下のような影響が生じる可能性があります:
-
法人設立の際、登記が受理されない/時間がかかる
-
就労継続支援A型事業の「指定」が受けられない
-
今後の事業拡大や転換の際に定款変更が必要となる
-
行政や地域社会からの信頼性に影響が出る
つまり、「目的」の書き方ひとつで、事業開始のスピードにも、将来の柔軟性にも大きな違いが出てくるのです。
A型事業の法人に求められる「目的」の条件とは?
就労継続支援A型事業の指定を受けるには、法人が「社会福祉法人」または「専ら社会福祉事業を行う者」であることが必要です。
ここでいう「専ら社会福祉事業を行う者」とは、定款の目的に福祉以外の事業が含まれていないことが前提となります。
たとえば、次のような表現は注意が必要です:
-
「不動産賃貸業」
-
「飲食店の経営」(※施設内での作業訓練を除く)
-
「一般雑貨の販売」など、福祉と直接関係のない営利事業
これらが定款の目的に含まれている場合、就労継続支援A型の指定申請が却下される可能性があるため、厳密なチェックが必要です。
目的の書き方一つで、申請が大きく遅れることも
法人設立や指定申請において、定款の目的記載に不備があると、「再提出」や「定款変更」が必要になり、開設スケジュールが大きく遅れるリスクがあります。場合によっては、法人設立後に一度解散し、再設立しなければならないケースすらあるのです。
せっかく「このタイミングで開設したい」という計画があっても、書類の不備で遅れてしまえば、物件の契約や採用計画にも支障が出かねません。
こうした事態を避けるためにも、定款の目的は最初にきちんと整理することが重要です。
なぜ、専門家に依頼するのがよいのか?
就労継続支援A型の指定申請や法人設立は、専門的な知識が必要な複雑な手続きです。定款の「目的」一つとっても、以下のような課題があります:
-
曖昧な表現を避けるための文言調整
-
自治体が求める記載水準との整合性
-
登記上の表現と、事業実態とのバランス
-
将来的な事業展開も見越した網羅性の確保
行政書士や司法書士といった専門家に依頼することで、これらの課題をスムーズにクリアでき、事業計画に集中できる環境が整います。
定款作成は、最初の“投資”と考えよう
「まずは自分で作ってみよう」と考える方も多いのですが、就労支援に特化した法人設立では、一般的な起業とは異なるルールが数多く存在します。
定款作成は、一見すると“紙の作業”に思えるかもしれませんが、その内容が今後の事業の可否を左右します。
安易に進めて後からやり直すことになれば、費用や時間のロスだけでなく、信頼にも関わる問題になりかねません。
定款作成は、将来の安心と信頼を得るための“先行投資”として、専門家に任せるのが賢明な判断です。
「始めたい」という気持ちを、確かな一歩に
就労継続支援A型事業は、利用者さんの「働きたい」という気持ちを支える、意義ある取り組みです。だからこそ、開設に向けた最初のステップである「定款作成」や「法人設立」は、丁寧かつ確実に進めることが求められます。
もし、書き方に迷っていたり、「これで大丈夫かな?」と少しでも不安がある場合は、専門家にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください。
あなたの想いに寄り添いながら、開業という大きな一歩を全力でサポートいたします。