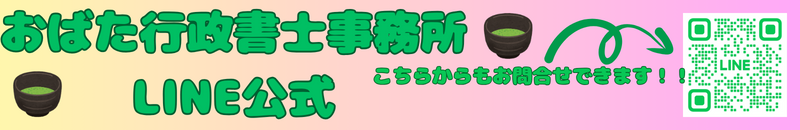ちょっと役立つコラム
10.122023
遺言書がないときの共同相続【静岡県の行政書士が解説】

遺言書がないときの共同相続とは?
大切なご家族が亡くなられた時、まず確認したいのが「遺言書」の有無です。
けれど、いくら探しても見つからない…。そんなとき、遺産はどうやって分けることになるのでしょうか?
今回は「遺言書がない場合の共同相続」について、できるだけ分かりやすく解説します。
1.遺産分割協議とは?
遺言書がない場合、亡くなった方の財産は、相続人全員が共同で所有している状態(共有)になります。
つまり「誰がどれを受け取るか」が決まるまでは、すべてが“みんなのモノ”ということです。
この状態を解消し、それぞれの相続分を決めるために必要になるのが「遺産分割協議」です。
相続人全員で話し合いをして、どの財産を誰が相続するのかを決めていきます。
遺言書で遺産分割を禁止していない限り、この協議はいつでも行うことができます(民法907条1項)。
2.遺産分割協議に加わる人は?
遺産分割協議の当事者は、相続人に限られません。具体的には以下のような人も含まれる場合があります:
-
相続分を譲り受けた人(譲受人)
-
包括受遺者(財産の一部ではなく、全体からの割合などで譲られた人)
-
家庭裁判所の許可を得た不在者財産管理人
-
未成年者が入所している児童福祉施設の施設長 など
なお、胎児がいる場合は、その誕生を待ってから協議を行う必要があります。出生後に、親権者などが代理人として協議に参加します。
3.遺産分割協議の方法と注意点
遺産分割協議には、特に決まった形式があるわけではありません。
たとえば、相続人が遠方にいる場合には、郵送やオンラインでの持ち回りによる協議も可能です。
また、協議の内容についても、法定相続分に厳密に従う必要はなく、相続人全員が納得すれば自由に決めることができます。
たとえば「長女がすべての不動産を取得し、他の相続人は預貯金を受け取る」なども有効です。
ただし注意したいのは、協議内容を明確に文書にしておかないと、後々のトラブルのもとになってしまうことです。
協議がまとまったら、その内容を書面にして、全員が署名・押印することで、後の誤解を防ぐことができます。
なぜ遺言書が大切なのか?
ここまでお読みいただいて、「思ったより複雑かも」と感じられた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そうなのです。
遺言書がない場合、相続人全員での話し合いが必要になり、協議が成立しない限り相続手続きは進みません。
しかし、相続人同士が必ずしも良好な関係であるとは限りません。
また、各相続人の生活状況や価値観の違いから、意見が食い違うこともあります。
実際に、相続をきっかけに関係が悪化してしまった…というご相談は少なくありません。
こうした状況を防ぐ手段のひとつが「遺言書」です。
遺言書があれば、誰にどの財産を残すかをあらかじめ明示でき、相続人の負担を大きく減らすことができます。
また、ご自身の想いや考えをきちんと残すことで、ご家族が迷わず手続きを進めることができます。
遺言書について考えてみませんか?
遺産をどう分けるかという話は、誰にとっても簡単なものではありません。
だからこそ、元気なうちに「自分の意思」を明確に残しておくことが、大切な人への思いやりにつながります。
遺言書を作ることは、特別な人だけが行うものではありません。
家族のことを想う、どんな方にとっても選択肢となりうるものです。
「どこから手をつければいいのかわからない」
「書いてみたいけど難しそう」
そんなときは、どうぞお気軽にご相談ください。
行政書士としてお手伝いできることがあります!!
📩【遺言書のご相談はこちらから】