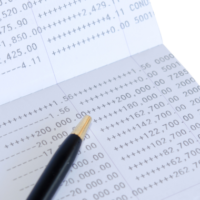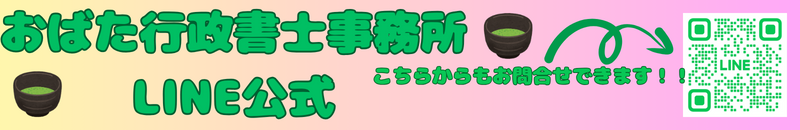ちょっと役立つコラム
10.262025
一人っ子で独身の人が亡くなったら相続はどうなる?遺言書で備えるべき理由【静岡県の行政書士が解説】

一人っ子で独身の場合、相続はどうなる?
「自分は一人っ子で独身。もし自分が亡くなったら、財産はどうなるのだろう?」
こうしたご相談をいただくことがあります。こういったケースって案外多いのではないでしょうか??
兄弟姉妹もいない、配偶者も子どももいないという場合、いざというときに相続人がいないように思えても、実際には“まったくいない”というケースは少し複雑です。
まず、民法の規定によると、相続人となる順番(法定相続人)は次のとおりです。
|
1.子(またはその代襲相続人) 2.直系尊属(両親、祖父母など) 3.兄弟姉妹(またはその代襲相続人) |
つまり、独身で子どもがいない場合、まずは「父母」や「祖父母」が相続人になります。
両親がすでに亡くなっている場合は、次に「兄弟姉妹」が相続人になります。
そして、兄弟姉妹もいない場合は、その代襲相続人(甥や姪)がいればその人たちが相続人になります。
ところが、一人っ子の場合、兄弟姉妹も甥姪もいません。両親・祖父母も他界しているとなると、相続人がまったく存在しない状態になります。
相続人がいないと財産はどうなるの?
相続人がいないまま亡くなった場合、遺産はどう処理されるのでしょうか。
このようなときは、家庭裁判所によって「相続財産管理人」が選任されます。管理人は故人の財産を調査し、債権者(お金を貸している人)や受遺者(遺言で財産をもらうことになっていた人)などに支払いを行います。
それでもなお財産が残った場合、最終的には「国庫(国のもの)」になります。
つまり、遺言書などがない場合、せっかく築いた財産はすべて国に帰属してしまうということです。
「自分には関係ない」と思っていませんか?
「親も高齢だし、自分が先に亡くなることなんてないだろう」
「財産といっても大したものはないから」
そう思う方も多いかもしれません。ですが、実際に“誰もいない”状態で亡くなると、残された家や預貯金、荷物の整理、葬儀費用の支払いなど、現実的な手続きを進める人がいません。
行政的な手続きは、すべて「相続人」や「遺言執行者」が行う前提になっているからです。
遺言もないまま亡くなった場合、葬儀を手配してくれる親しい友人や知人がいたとしても、法律上の権限がないため、銀行口座の解約や不動産の処分などはできません。
つまり、何も手を打たずに亡くなると、周囲の人が非常に困ってしまうことになるのです。
「遺言書」が果たす大きな役割
こうしたケースでとても重要なのが「遺言書」です。
遺言書は、自分の財産をどのように扱ってほしいかを、自分の意思で示すことができる唯一の方法です。
たとえば、次のような内容を決めておくことができます。
|
親しい友人やお世話になった人に財産を贈る 遺産の一部を寄付する 遺言執行者を指定し、死後の手続きを任せる 葬儀の方法や納骨先を指定する |
遺言があれば、たとえ相続人がいなくても、その内容に基づいて確実に手続きを進めることができます。
自筆証書遺言の保管制度を活用して
「遺言書」と聞くと、作成が難しそうな印象を持つ方もいますが、今は「自筆証書遺言の保管制度」を利用することで、手軽かつ安全に保管できるようになりました。
法務局で保管すれば、紛失や改ざんの心配もなく、死後にスムーズに内容を確認してもらうことができます。
また、遺言書の作成時には行政書士が文面の作成をサポートすることもできます(ただし、保管や提出はご本人が行う必要があります)。
「誰かに迷惑をかけたくない」その思いを形に
「身寄りがないから、誰かに迷惑をかけてしまうのでは…」
そんな不安を抱える方にこそ、遺言書は大切な備えです。
自分の意思で終わりを整えておくことは、「誰かに迷惑をかけないため」だけでなく、「自分らしい生き方を最後まで貫くため」でもあります。
「自分がいなくなったあと、どうなるのか」
少しでも気になったときが、考え始めるタイミングです。
難しい内容も、行政書士に相談すれば、一緒に整理しながら形にしていくことができます。
まとめ
一人っ子で独身という状況では、亡くなったあとに相続人が存在しないことも珍しくありません。
その場合、財産は国に帰属し、あなたの想いが反映されないまま終わってしまいます。
だからこそ、生前のうちに「自分の意思を残す」準備をしておくことが大切です。
遺言書は、未来に託すための“最後のメッセージ”。
あなたの歩んできた人生を、きちんと次につなげるための方法なのです。
おばた行政書士事務所では遺言書の作成のサポートを行っています。
まずはお気軽にお問い合わせください。