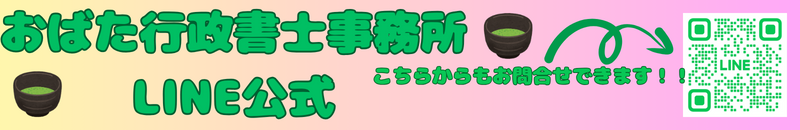ちょっと役立つコラム
5.52025
実は気になる?抹茶と法律の関係【静岡県の抹茶好き行政書士が解説】

抹茶が好きな方は多いと思います。お菓子に、ドリンクに、お料理に——身近な存在になった抹茶ですが、ふと「抹茶って何か法律に関係あるのかな?」と思ったことはありませんか?
今回は、抹茶に直接関わる法律はあるのか、そしてどんなルールのもとに私たちの元へ届いているのかを、やさしくご紹介します。
「抹茶に関する法律」はあるの?
実は、「抹茶」にだけを対象にした法律は存在していません。ただし、抹茶を含むお茶や食品に関しては、さまざまなルールが関係してきます。
食品表示法と抹茶
まず大事なのは「食品表示法」。抹茶も「食品」のひとつなので、原材料名、原産地、賞味期限などを表示する義務があります。
たとえば、外国産の抹茶を使っていながら「国産抹茶」と記載すれば、これは違法になります。消費者に誤解を与える表示は禁止されているのです。
業界の自主基準もあります
公益社団法人 日本茶業中央会では、「緑茶の表示基準」というガイドラインを定めています。これは法律ではないものの、業界として正確な情報提供をしようという取り組みです。
お茶を支える法律もあります
2011年に「お茶の振興に関する法律」が制定されました。お茶の消費拡大や文化継承、生産者支援を目的とした法律で、抹茶もこの対象に含まれます。
これにより、抹茶の輸出支援やブランド化、海外でのプロモーション活動も後押しされています。
茶業及びお茶の文化の振興に関する基本方針について【農林水産省】
広告・ラベル表示には注意が必要
「景品表示法」という法律では、実際と異なる内容を広告に使うことを禁止しています。
たとえば、ほんの少ししか抹茶が入っていないのに「濃厚抹茶!」と誤解を招くような表現をすれば、問題になる可能性があります。
まとめ
抹茶に直接関係する法律はないものの、食品としてのルールや業界基準、そして日本のお茶文化を守る法律によって、しっかりと支えられています。
ふだん何気なく手に取っている抹茶製品も、実はこうした「見えないルール」の中で私たちの元に届いているのですね。
抹茶好き行政書士としては、こうした制度や表示ルールの背景を知ることで、「表示内容は本当に正確かな?」と気にしてみる視点も大切だと感じています。
おばた行政書士事務所は、抹茶が好き過ぎて抹茶色の事務所と抹茶色の車で活動しています。
まずはお気軽にお問い合わせください。